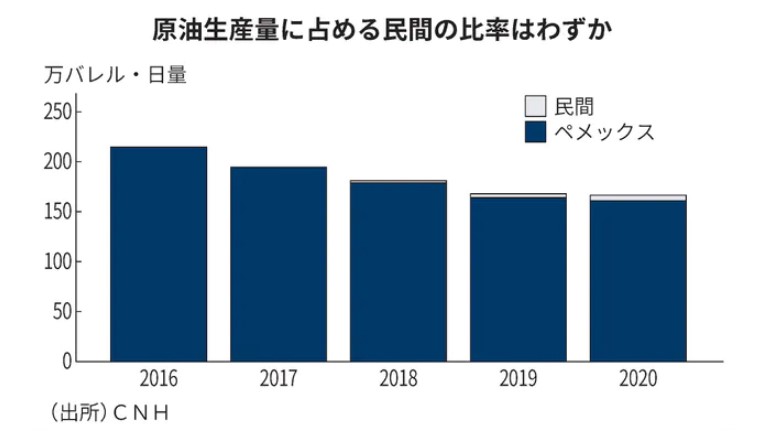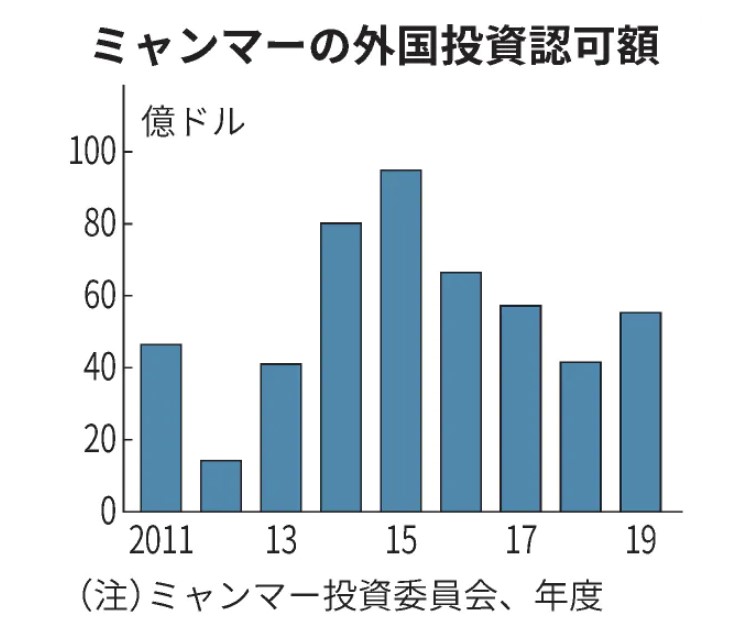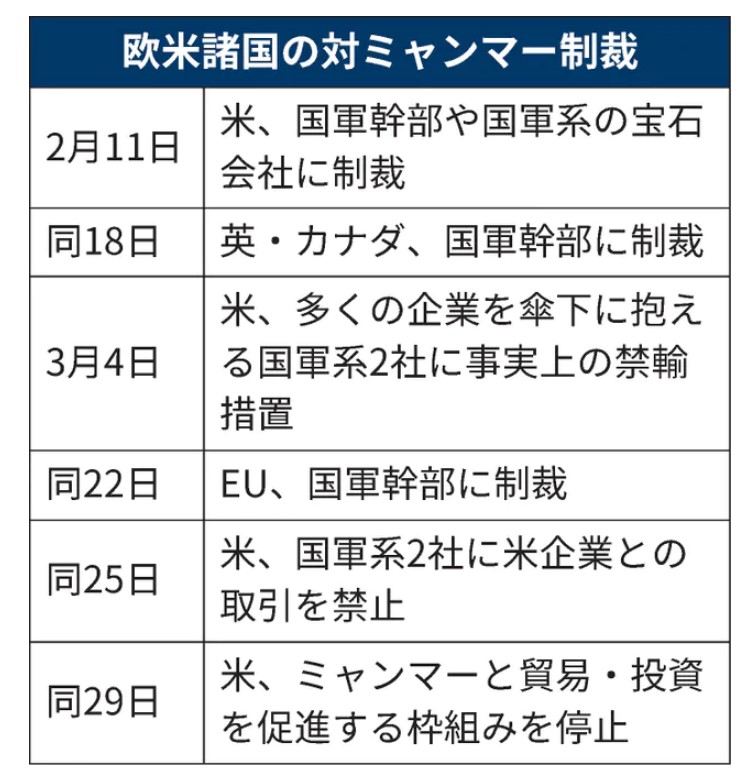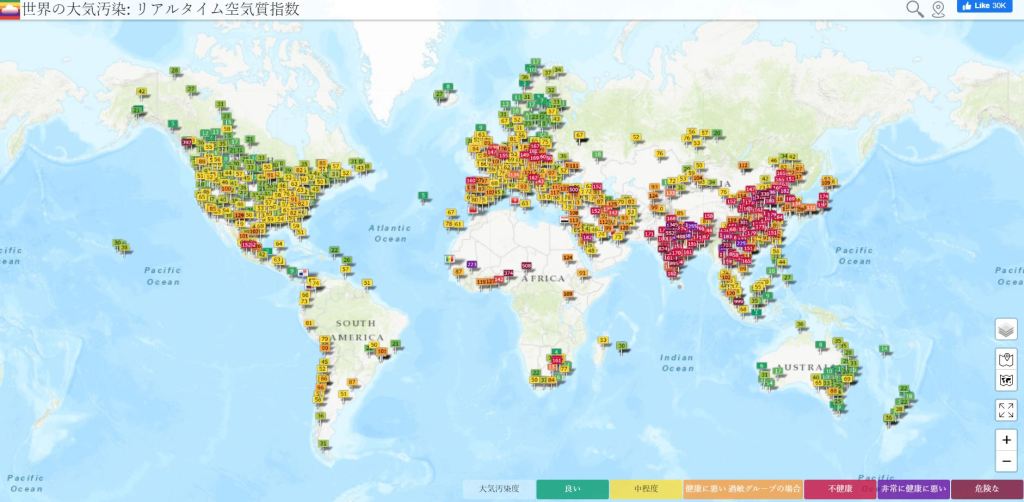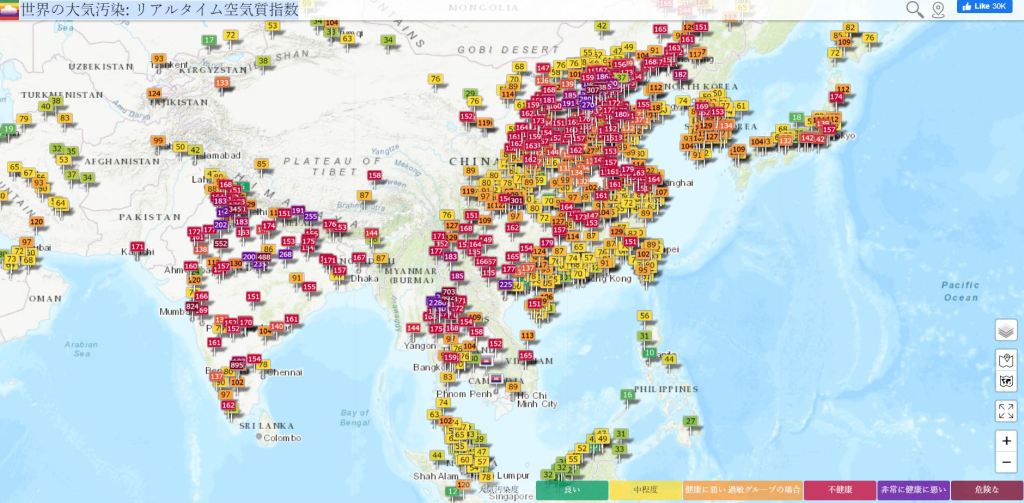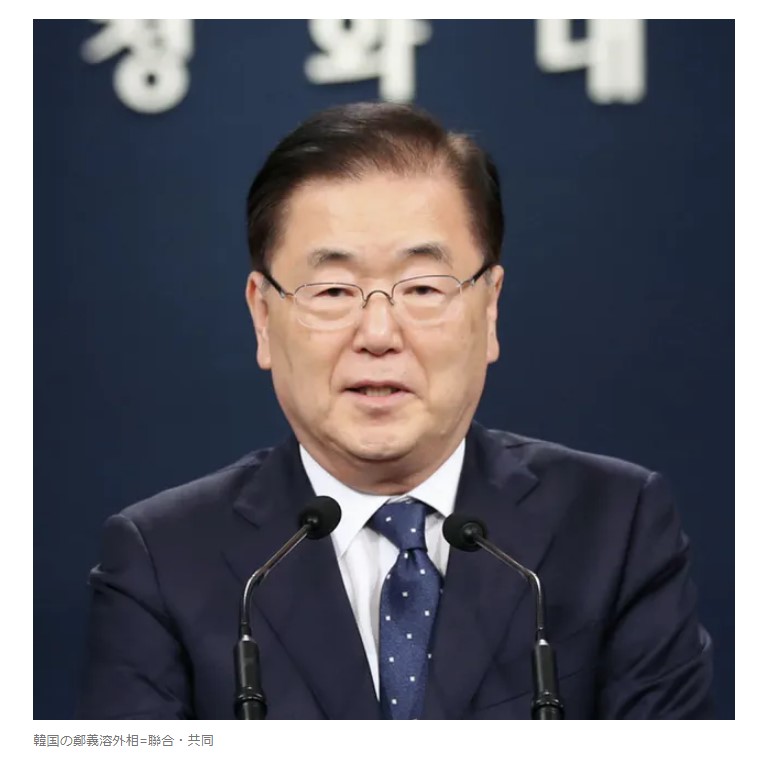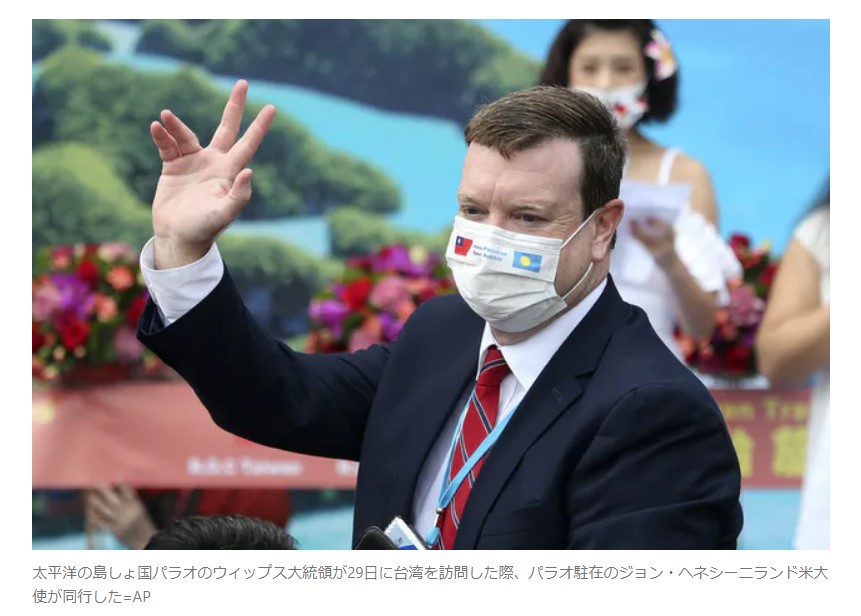https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN30DMP0Q1A330C2000000/

『【サンパウロ=外山尚之】ブラジルのボルソナロ政権で閣僚や軍幹部の離反が相次いでいる。大統領は29日、外相や防衛相を含む6閣僚を交代させると発表したが、新型コロナウイルス対策の失敗で支持率が低迷している。同氏の支持基盤だった軍との対立も表面化、30日には陸軍・海軍・空軍の司令官が同時に退任した。2022年の大統領選に向け左派陣営の巻き返しも進んでおり、ボルソナロ氏は窮地に立たされている。
19年1月の大統領就任以来、頻繁に閣僚交代を繰り返してきたボルソナロ氏だが、今回の内閣改造は政権発足以来、最大の規模となる。コロナワクチンの確保に失敗したとして議会の圧力でアラウジョ外相が辞任せざるを得ない状況となり、「政府が脆弱な時期を迎えているという説を否定するため」(経済紙バロル・エコノミコ)という見方が一般的だ。
今回、国内に大きな衝撃をもたらしたのが、アゼベド防衛相の交代だ。元陸軍大将のアゼベド氏は軍出身のボルソナロ氏に請われる形で防衛相に就任。20年5月にボルソナロ氏が対立する裁判官や州知事らを批判する文脈で軍による司法などへの介入を示唆した際も、「軍は法と秩序、民主主義、そして自由の側にいる」と発表し、事態の鎮静化を図るなど、政権の重しとなっていた。
アゼベド氏は退任にあてて公開した声明で「任期中、私は軍を国家の組織として守った」として、軍の私物化をにおわせるボルソナロ氏をけん制した。3月に入りボルソナロ氏は新型コロナの感染再拡大で州政府が実施する経済制限に対して法的根拠なく軍の出動を求め、アゼベド氏と対立していたとされる。軍内部には過去の軍政を礼賛するボルソナロ氏の過激な思想に同調する兵士も多いが、アゼベド氏は軍としての規律の重要性を身をもって伝えた形だ。
軍上層部との間にすきま風が吹く中、ボルソナロ氏は追い詰められつつある。投資助言会社XPインベスチメントスが12日に発表した世論調査によると、同氏の不支持率は45%と、支持率の30%を大きく上回った。新型コロナの第2波が深刻化する中、批判が強まっており、岩盤支持層である保守派に迎合することで無党派層の支持が離れるという悪循環が始まっている。
ボルソナロ政権は新型コロナ対策として低所得者層向けの現金給付策の再開を決定している。現金給付とともに支持率が上昇した昨年の再現をもくろむが、狙い通りに進むかは不透明だ。
首都ブラジリアの連邦裁判所では任期中の汚職事件で有罪判決を受けたルラ元大統領の過去の裁判の再審理が予定されている。22年10月に予定されている大統領選までに有罪判決が確定しなければ、ルラ氏は立候補が可能となる。低所得者層からカリスマ的な人気を誇るルラ氏が大統領選に出馬すれば、ボルソナロ氏は厳しい戦いを強いられる。
春割ですべての記事が読み放題
今なら2カ月無料!
ログインする
https://www.nikkei.com/login 』
『生い立ち
サンパウロ州グリセーリオに生まれ、ジャイールの父ペルシ・ジェラルド・ボルソナーロと母オリンダ・ボントゥリ・ボルソナーロはイタリアとドイツに先祖をもつヨーロッパ系移民だった[16]。父ジェラルドは1980年代にアマゾン金鉱で金を求めて過酷な労働に耐えた鉱山労働者の一人だった[17]。』
『軍歴
陸軍士官学校を卒業後[18]、1974年にアグーリャス・ネーグラス軍事学校に入学し、1977年に卒業した。1979年から1981年まで、マット・グロッソ・ド・スール州のニオケの第九野戦砲兵連隊に所属したのち、リオデジャネイロ州のパラシュート歩兵旅団に参加する[19]。1983年、彼は軍体育学校で体育の訓練を受け、教師となり、歩兵旅団を退団する。
1980年代にブラジル軍によってつくられた秘密文書には、「財政および経済への過度の野心」を[20]持つ人物だと評されている。
軍時代の上司カルロス・アルフレッド・ペレグリーノ( Carlos Alfredo Pellegrino)大佐のボルソナーロ評。
ボルソナーロはいつも大尉たちのあいだで指導的役割を取ろうとして、反対にあっていた。その理由は同僚への攻撃的な扱いだった。彼の主張には、論理と合理性とバランスが欠けていた。』
『経済
2018年の大統領選挙の投票でボルソナーロが急に注目されたことによって、市場でのリバウンドが起こり地域と現実の株価が回復した。 一部のアナリストによると、これは投資家の信頼が決選投票でのボルソナーロ勝利の方向にあるためだという[84]。
ボルソナーロは自身の経済顧問は市場原理主義を代表するミルトン・フリードマンを生んだシカゴ学派経済学者である博士パウロ・ゲデス(ポルトガル語版)であると公式に述べている。パウロ・ゲデスによると、ブラジルの国家経済における最大の問題の1つは「リソースと権力の集中が政治を腐敗させ、経済を停滞させていること」、それは「機能不全の状態」であり、「国家はすべてに干渉し、すべてに介入するが、分配は最小限であり、リソースの消費は最大限となっている」とする。ゲデスの主要な懸念事項のもう一つは、ブラジルの公的債務の膨らみであり、これは利息の年間支払が過大であることを意味する。 一方、ボルソナーロは富裕層の人々の所得税を減らすためのゲデスの考え方を拒絶したと表明した[85]。
ボルソナーロは「プレサル― pré-sal(ブラジルの大規模油田[86][87])」の採掘開始に賛成票を投じ、「自由市場がこそ自由の母である[88]」と主張している。これまでのボルソナーロの政策決定は必ずしも自由主義者とは言えない面も指摘されているが、その目標はロナルド・レーガンを参考にした経済的自由主義である[89]。』