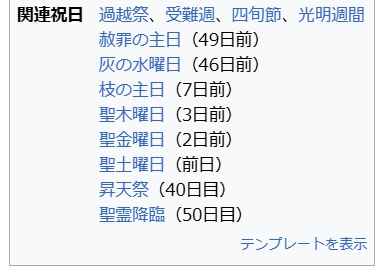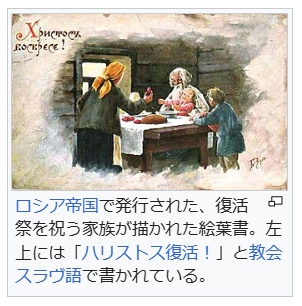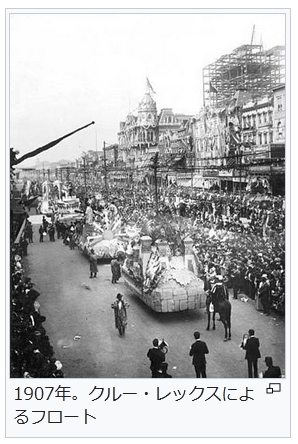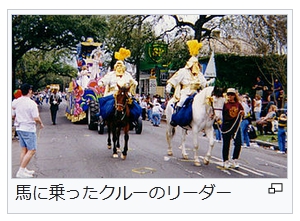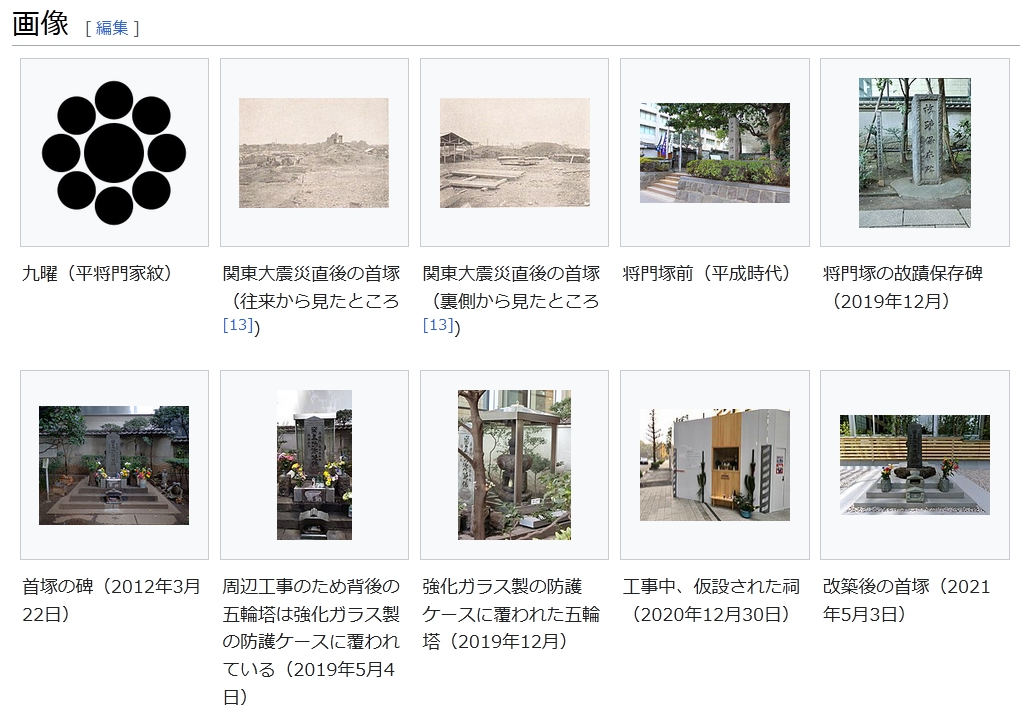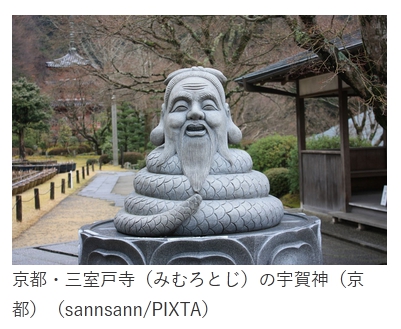生命主義とキリスト教
ー米国の中絶論争に学ぶー
田島靖貝|」・
https://core.ac.uk/download/pdf/228944441.pdf
『I抄録
日本では一般に,「人命は地球より重い」という生命主義的価値観があると信じられてい
る。一方で,人工妊娠中絶には大いに寛容であり,「中絶天国」などという自嘲的な評価さえ存在する。
一方米国では,人工妊娠中絶を巡る論争,いわゆる プロライフープロチョイ
ス論争」は国を二分する大議論となって久しい。特に,米国の倫理的価値判断に強い影響力をもつキリスト教会における議論のゆくえには,大いに興味をそそられる。
本論文において
は,特に「全米プロライフ宗教協議会J ( National Pro4ife Religious Council)と,|_産児選
択宗教連合」(The Religious Coalition for Reproductive Choice)に属するキリスト者たち
の主張に耳を傾ける。
同じキリスト教信仰に立ちながらも,両陣営に分かれて議論を戦わせ
る彼らの意見に傾聴し,人工妊娠中絶という苦渋の選択をなそうとする女性と,生まれ出よ
うとする胎児,その両者の隣人となるための方法を考える。
Key words:人工妊娠中絶 生命主義 プロライフープロチョイス
全米プロライフ宗教協議会 産児選択宗教連合
~序~
「人命は地球より重い」。これは,1977年に勃発
した日本赤軍によるダッカ日航機ハイジャック事
件の際に,福田赳夫首相が発した言葉である。
以来,我が国における生命主義的思考をリードする
スローガンとなってきた観がある。「人命救助はあ
らゆる事柄に優先する」。
これは,古来より我が国
に存在した至上的な価値観であるとは言い難い。
わざわざ文献を紐解いてみるまでもなく,誰もが
「姥捨て」や「間引き」について聞き知っているこ
- T ajima, Yasunori
九州ルーテル学院大学助教授
とだろう。
また極めて不快な表現であるが,「中絶
天国」などという自嘲的な言葉さえ囁かれている。
もしも,「人命は地球より重い」というのであれ
ば,その根拠が示されて然るべきであろう。
日本
国憲法は第13条において,国民の「生命,自由,
幸福の追求」についての権利を最大限尊重すると
謳っているが,明確に「国民」としての認知を受
けられない「人命」については沈黙を守っている。
具体的にいえば,胎児については未だ「国民」と
認知されるには至らない存在であるから,「地球よ
り重い人命」を持つとはみなされていない。
いうまでもないことであるが,人格をともなっ
た生命がいつどの時点で誕生したと認められるの
19
ルーテル学院研究紀要No.40 2006
かについては,万国共通の基準というものは存在
しない。
「生命」が「人命」へと変化する瞬間を,
だれもが特定できるわけではない。
また,そもそ
も「人命」ではないヒトの「生命」などありえな
いとする主張も少なからず存在する。
その代表格
は,ローマ・カトリック教会が主張する「霊魂の
即時賦与説」であり,「人格」と「生命」の分離を
許容しない「生命主義」の主張である。
我が国では現在ほとんど議論にすらならない人
エ妊娠中絶の是非の問題も,米国においては国論
を二分する大議論となって久しい。いわゆる「プ
ロライフープロチョイス論争」である。
文部科学省は1997年の神戸連続児童殺傷事件以
来,「命を大切にする教育」に積極的に取り組む姿
勢を見せてきたが,その効果が上がっていないこ
とは,親殺し子殺しが頻発する昨今の情勢を見て
も明らかである。「命の大切さ」を自明のこととし
て語る従来の方法は,どこか上滑りで説得力に欠
けるのである。
米国(75プロライフープロチョイス論争」は,遠
くから冷めた目で眺める限り,そのなりふり構わ
ぬところがどうかすると滑稽にすら映る。
しかし,
「人命」をめぐる問題で大の大人が口角泡を飛ばし
て議論する姿こそ,現在の日本に決定的に欠けて
いるものではないだろうか。
子供たちは,大人の
語る「命の大切さ」が単なるお題目に成り下がっ
ていることを敏感に感じ取っている。
我が国が
陥ってしまった人命軽視の現状から抜け出すヒン
卜が,米国で熱く繰り広げられる「プロライフー
プロチョイス論争」にあると私は考えているので
ある。
I米国の中絶論争
1-1ロウ対ウェイド判決
いわゆる「プロライフープロチョイス論争」は,
単純化して語ればr生命主義」の陣営と,r人間の
選択の自由」を「女性の権利」という視点で主張
する「自律主義」陣営との戦いである。
論争の発端は,よく知られた1973年の米国連邦
最高裁における「ロウ対ウェイド判決」にある。
1970年,テキサス州ダラス在住の独身女性ジェー
ン•ロウ(仮名)が,当時すべての中絶を禁じて
いたテキサス州法を違憲であるとし,有能な資格
者である医師の手によって,安全に,しかも医療
設備の整った病院で合法的に中絶手術を受ける権
利を主張した。彼女は当時妊娠中であった。(Baird
and Rosenbaum, 2001,63)
これは意外なことかもしれないが,米国では
1865年より1970年まで,すべての州で人工妊娠中
絶は非合法とされていた。
そのために素人の手に
よって秘密裏に行われる中絶行為が横行し,多く
の女性が犠牲となり命を落としてきたという経緯
があった。
1970年にハワイ州が中絶を合法化した
のを皮切りに,「ロウ対ウェイド判決」が下される
までの間にも,実に18の州が次々と中絶を合法化
していった。
「ロウ対ウェイド判決」によって,米国における
全面的な中絶禁止は,憲法の定めるプライバシー
権行使の不当な制限にあたると認められ,違憲と
された。
ただしその際,妊娠の中断について女性
の権利が無制限に認められたのではない。連邦最
高裁は胎児の人権についての,いわゆる「妊娠期
間の三期説(trimester system)」を提示し,胎児
の母体外における「生存可能性(viability) J確立
とともに胎児の人権確立の可能性も高くなるとし
た。
そこで具体的に裁判所が提示した「生存可能
性」確立の時期は,妊娠24〜28週であった。(Pence,
2000,173)
1-2「プロライフ派」の主張
1987年に公表されたローマ・カトリツク教会の
『生命のはじまりに関する教書』は,奇しくも現在
のローマ教皇ベネディクト16世が,教皇庁教理省
長官時代に手がけた文書である。
その第一章では,
「人間は,その存在の最初の瞬間から人間として尊
重されるべきである」と宣言され,第二バチカン
公会議の決定である『現代世界憲章』にある文言,
「生命は受胎されたときから最高の配慮をもって守
らなければならない。人工中絶や赤子殺しはもっ
20
生命主義とキリスト教
とも恐ろしい犯罪である」を引用し,いわゆる受
精時における「霊魂の即時賦与」について繰り返
し述べている。
また同時に,生命倫理における主
要な議論の一つである,「人格の獲得時期」につい
ての議論に加えて,「生存可能性」についての議論
そのものをもはっきりと否定している。(教皇庁教
理省,1987)
一方,特に米国において,教義上はローマ・カ
トリック教会から遠いとみられるプロテスタント
諸教会に属する「プロライフ派」の人々は,こと
人工妊娠中絶に関しては,神学上の相違を飛び越
えてローマ・カトリツク教会の主張と軌を一にし
ているように見える。
「プロライフ派」の超教派団
体である「全米プロライフ宗教協議会」(National
Pro4ife Religious Council)には,米国福音ルーテ
ル教会,ミズーリ派ルーテル教会をはじめ,米国
長老派教会,ユナイテッド・メソジスト教会,ユ
ナイテッド・チャーチ・オブ・クライスト,そし
てローマ・カトリツク教会などの教職有志・信徒
有志が加盟している。
このNPRCの呼びかけに
よって作られた「プロライフ説教集」である“ The
Right Choice”から,彼らの主張を拾ってみたい。
ユニオン神学校 ヴァージニア州リッチモンド)
で助教授として聖書学,説教学を教えるエリザベ
ス・アクティマイアT Elizabeth Achtemeier)は,
中絶問題を,自殺帯助や安楽死,高齢者への医療
制限などと同列に論じている。
また,自分が「プ
ロライフ」であることの聖書的根拠は,まず出エ
ジプト記20章3節にある十戒の「殺してはならな
い」にあると述べる。
加えて胎児の遺伝的固有性
にも触れ,胎児の創造が神の業であることを主張
する。
詩編24編1節「地とそこに満ちるもの,世
界とそこに住むものは,主のもの。」によって,
我々の命は我々自身の所有ではないと述べている。
さらに創世記4章9節のカインの言葉にある「弟
の番人」(brother’s keeper)を引用し,我々はお
互い支え合う存在であるから,たとえば15オの少
女の妊娠も,もはや彼女の個人的な問題ではなく,
キリストの愛においてそれは「我々の問題」とな
り,また「教会の問題」となるという。
そこで有
名なマザーテレサの言葉,「もしあなたに子供は
要らないなら,私にください。私は要ります。」を
引用し,これを実行に移すべきだと主張する。
つまり,女性が中絶を選択するのは,誰の助けも得
られないからであり,教会の「問題のある妊娠委
員会」は,胎児の祝福式をし,ベビー服を用意し,
医療的経済的サポートをなし,職業訓練,教育,力
ウンセリング,住居の提供,そして望まれるなら
ば養子縁組の手配をすることができるというわけ
である。
最後に彼女は,友人の牧師から聞いた話
として,ある一人の中絶常習者となってしまった
女性のエピソードを紹介している。
その女性はカ
ウンセリング・センターや友人たちから助けを得
たいと思っていたが,得られたのは彼女の行為に
ついての言い訳ばかりで,彼女は一向に安心でき
ないでいた。
最後に彼女は近所の教会へ行き,牧
師にすべてを打ち明けた。
牧師が彼女に,「あなた
は誤ったことをした。」と言うと,彼女は,|’その
言葉を聞きたかったのです!」と答えたという。
そこではじめてこの女性には悔い改めが生まれ,
そして彼女は福音の赦しを受け取ったというので
ある。
アクティマイアーはすべての牧師に,少な
くとも1年に1回は日曜日の礼拝で「生命の神聖
主日」(Sanctity of Life Sunday)の説教をする
ことを勧めている。(Stallsworth, 1997, 19-27)
ユナイテッド・メソジスト教会のコニー・
ロ ーランド・アルト牧師(Connie Roland AIt)
は,1993年1月の礼拝説教において,子宮内に
ある「赤ちゃん」は人格を持った人間ではない
と判断することを,「嘘」であると断じている。
また,金の亡者でその収入が絶たれることを恐
れる中絶医師たちによって,女性たちは「襲わ
れている」と手厳しい批判を展開する。
最後に
彼女は,インドのマハトマ,ガンディーの言葉
「非暴力と真実とは分離できない,それぞれ一方
のみで存在することはありえない」を引用し,
中絶をなくし,傷ついた女性たちを受け入れよ
うと勧めている。(Stallsworth, 1997, 29-33)
ユナイテッド・チャーチ・オブ・クライストの
ジョン・ブラウン牧師(John B. Brown)は,1989
21
ルーテル学院研究紀要No.40
2006
年1月の礼拝説教において,「我々はすべて,男も
女も,老いも若きも,神の恵みを必要としている」
と述べている。
私はここに,反セクシズム,反エ
イジズムの主張を読み取っている。すなわち,中
絶は胎児に対する年齢による差別に他ならないと
いう主張である。
加えてブラウンは,この社会に「霊的道徳的
オンチ」とでもいうべき男女が増えているとい
う。
そして,「責任を欠いた自由」を求める欲望
を持つ人が多くなっていると警告する。
さらに
「プロチョイス」の語彙には,「子宮を一掃する」
「妊娠の終局」,生まれる前の子供を「胎児」と
呼ぶこと,「廃棄物]パラサイトI懐胎の産物」
「原形質の塊」「人間になる前の組織体」などの
「女宛曲語法」に満ちていると指摘する。
彼の主張
によれば,どのような呼ばれ方にせよ,とにか
くすべての人間存在は尊厳と価値を持つという
こ <とである。(Stallsw orth,1997, 35- 41)
ミズーリ派ルーテル教会のポール・クラーク牧
師(PaulM. Clark)は,1995年1月の礼拝説教に
おいて,エレミヤ書1章5節T「わたしはあなたを
母の胎内に造る前からあなたを知っていた。母の
胎から生まれる前にわたしはあなたを聖別し諸国
民の預言者として立てた。」に言及し,尊厳
(dignity)の意味について語っている。
原語である
ラテン語のdignitasには,「仕事」!_功績」といった
意味があることに着目し,人間は神のT仕事」によ
り存在するゆえに尊厳を持つと説明する。
尊厳の
根拠は,我々が何をするカXできるか)ということ
とは無関係であるという極めてルター派的な説明
がなされている。
しかし同時に,「もし生命が,変
化の連続の中におかれているどろどろした太古の
海から進化論的に発生したのなら,人命を守るこ
とは重要ではないだろう」という聖書原理主義的
主張が顔をのぞかせる。(Stallsworth, 1997, 43-48)
同じくミズーリ派ルーテル教会のエドワード・
フェスケンス牧師(Edward Fehskens)は,1994
年11月のLutherans for Life全国集会の礼拝で,
「毎年11〇万人の子供が婚外妊娠によって生まれて
いる,これは全出生数の30%に近い」「1991年に,
白人の子供の22%,黒人の子供の67%がシングル
マザーのもとに生まれている」「全出生数のうち
26%が非嫡出子である」「毎年100万人の子供が,
両親の離婚・別離を経験している」「1990年代に生
まれた子供のうち約60%が子供時代に父親不在で
あった『今日,50%の子供が片親だけと暮らした
経験をもつ」などの統計を示し,男が神から与え
られた使命を放棄していることで,女性と子供が
苦しんでいるという主張を展開している。
加えて
「もし女性には中絶を選ぶ権利があるというなら
ば,胎児の父親には何の権利もないということに
なる」といって「プロチョイス」の立場を牽制す
る。(Stallsworth, 1997, 49-56)
彼の主張を貫い
ているのは,1990年代に全米で大きな運動を展開
した「プロミス・キーパーズ」の価値観,すなわ
ち「父性の復権」である。
ユナイテッド・メソジスト教会牧師であり,メ
リーランド州ボルティモアにあるセントメアリー
大学・神学校の新約学教授であるマイケル・ゴー
マン(Michael J. Gorman)は,1994年!.月の主日
説教において,ル力による福音書io章にある「良
いサマリヤ人のたとえ」を用いて,|・誰が強盗に襲
われた人の隣人になったのか?」というイエスの
問いが,隣人の!’基準j( criteria)を問うているの
ではなく,その人の!_品性J( character)を問うて
いるのだと指摘する。
正しい問いかけは,「隣人と
して存在すること」についてなのであって「隣人
を定義すること」についてではなかったことに着
目する。
そこから導き出されることは,「胎児は厳
密な意味で人間といえるのか?」という問いは間
違っており,むしる どうしたら我々・教会は,困
難な妊娠によって中絶を考えざるを得ない女性や
少年やその家族の隣人となることができるか?」
という問いこそ正しいということである。
「良いサ
マリヤ人」としての教会は,女性と子供の両者を
隣人として認識することを学ぶべきであり,その
両方の隣人となるべきであるという持論を展開す
る。(Stallsworth, 1997, 57- 60)
ローマ・カトリック教会司祭であるリチャード・
ジョン・ニューハウス(Richard John Neuhaus)
22
生命主義とキリスト教
は,1993年6月に行われた「全米いのちの権利大
会」において,「プロライフ運動のゴールは,政治
的にも文化的にも,胎児への最大限の法的擁護が
支持されることである」と述べている。
「ロウ対ウ
エイド判決」は「プライバシー」を,「家族計画連
盟対ケイシー判決」(1992年連邦最高裁判決505 U.
S.833)では「自由」を産児調整のコンセプトとし
ているが,どちらも結果は同じであり,胎児,昏
睡状態の人,認知症の人,老衰状態の人などは選
択の自由」がないことは明らかであるという。
宗
教は究極的関心,すなわち存在の概念,意味の概
念,宇宙の概念,人命の神秘についての概念など
を専門として取り扱うが,連邦最高裁は「自己絶
対化の宗教」を創り出してしまったと批判する。
胎児は疑いなく独自の遺伝子構造を持つ生命に他
ならないという主張を展開している。(Stallsworth,
1997, 61-68)
同じく ローマ・カトリック教会のニューヨーク
大司教であるジョン・オコナー(John Cardinal0′
Connor)は,1993年1月の礼拝説教において,中
絶に関して問題となるのは「恐れ」であると述べ
ている。
すなわち,中絶に直面している女性たち
の恐れとは,「子供の面倒は見られないという恐
れ]子供を養い手助けすることはできないという
恐れ」「子供の父親が去っていくという恐れ」「子
供が身体障害知的障害かもしれないという恐れ」
「大学で学べなくなるという恐れ」「仕事を失うと
いう恐れ」!’それほど重大ではないにもかかわら
ず,重要だと思える事柄への恐れj体形が崩れる
という恐れ]男の子が欲しかったのに女の子を妊
娠したという恐れ」またはその逆のケースなどで
ある。
恐れは暴力を生み,それが胎児の死を招く
というのである。(Stallsworth, 1997, 69-76)
ローマ・カトリック教会司祭であるフランク・
ペイボーン(Frank A. Pavone)は1995年に行っ
た礼拝説教において,中絶の決断は女性の自由な
決定として作用しているのではなく,その女性の
子宮にいる子供の「生か死か」の決断として作用
しているのであると述べる。
我々の兄弟姉妹のま
さにその命が,中絶の決断で危うくされていると
いう主張である。
これがどうして「プライバシー
の問題」だと言えるだろうかと述べている。
(Stallsw orth, 1997, 77-80)
長老派教会牧師であるテリー・シュロスバーグ
(Terry Schlossberg)は,1995年に行った礼拝説
教において,中絶を巡る論争は,「この宇宙には目
的と意味がある」という主張と,「この宇宙にはカ
オスのみがある」という主張との衝突であると述
ベている。
つまりそれは,信仰と不信仰,希望と
絶望,愛と愛の欠如との車L株だというわけである。
そこで,中絶しないという選択肢を提供するため
に,十代で未婚の少女を教会員の家庭に迎え入れ,
妊娠期間に必要な場所を提供することを勧めるの
である。(Stallsworth, 1997, 81-87)
長老派教会牧師であるベンジャミン・シェルド
ン(Benjamin E. Sheldon)は,1989年1月の礼拝
説教において,メアリー・プライド(Mary Pride)
の言葉を引用して,「家族計画が出現した50年代
には,女性の母性に疑問が投げかけられるように
なった。
60年代には,中絶の権利が主張された。
70年代には,中絶は合法化され,母性は人生の選択
肢の一つになった。
そして今日,母性というもの
は単なる趣味ということになってしまった。」と述
ベ,現代社会には「反子供J( anti-child)の先入観
が蔓延していることを憂慮する。
すべての子供は,
生まれた後も生まれる前も神によって創造され,
愛され,神のためにケアを受ける存在であると述
ベ,詩編139編13節の「あなたは,わたしの内臓
を造り,母の胎内にわたしを組み立ててくださっ
た。」とエレミヤ書1章5節の「わたしはあなたを
母の胎内に造る前からあなたを知っていた。母の
胎から生まれる前にわたしはあなたを聖別し諸国
民の預言者として立てた。」を引用し,すべての人
ば 胎児も含めて),固有の人格をもち,神によつ
て知られる独立した存在なのだと述べている。
(Stallsw orth, 1997, 89-94)
ローマ・カトリツク教会の修道女マザー・テレ
サ(Mother Teresa)は,1994年2月3日にワシ
ントンD.C.で行われた朝祷会において,「どの子供
も神の姿に似せて創造され,愛するため,愛され
23
ルーテル学院研究紀要No.40 2006
るために生まれます」と述べている。
また,「拒絶
され,望まれず,愛されず,恐ろしがられている
と感じている人々,社会から締め出されている
人々,こういった人々の霊的貧困こそもっとも克
服困難なものです。
そして避妊,中絶といった行
為は,人々に霊的貧困をもたらします。これこそ
最悪の,もっとも克服困難な貧困なのです。」と述
べている。
そしてイザヤ書49章15節をパラフレー
ズして, 「 たとえ母親が子宮の中の子供を忘れるこ
とがあったとしても,そんなことはあり得ないで
しょうが,たとえ母親が忘れるとしても,『私は決
してあなたを忘れない』と書いてあります」と
語っている。(Stallsworth, 1997,101-109)
ミズーリ派ルーテル教会のチャールズ・ホワイ
テッド Jr•牧師(Charles E. Whited, Jr.)は,1995
年1月に行った礼拝説教において,現代の状況は
初代キリスト教会時代にコリントの教会が陥った
状況と似ていると述べ,我々の社会は「性的不道
徳」を受け入れ,また大目に見ていると厳しく指
摘している。
つまり中絶の容認は,「性的不道徳」
の容認と同一視されているのである。(Stallsw orth,
1997, 111- 116)
1-3プロチョイス派の主張
米国において,我が国の厚生労働省に相当する
機関である Department of Health and Hum an
Servicesにて家族計画局の責任者を務めるゲイ
リー・クラム(Gary Crum)は,自らプロライフ
を標榜する生命倫理学者であるが,彼によればプ
ロチョイス派が中絶容認のために掲げる理由は,
以下の8点に分類できる。(Crum, 1992, 11-23)
1)中絶は,結果的に社会福祉政策のコスト削減
につながる。
2 )中絶は,被虐待児童の数を減らし,苦しみを
減少させる。
3 )中絶は,貧困家庭の数を減らし,苦しみを減
少させる。
4 )(妊娠によって)死の危機に瀕している女性か
ら胎児を取り出して妊娠を中止することが許
されるなら,中絶もまた許されるべきである。
5 )強姦の犠牲となって妊娠した女性から,不必
要な苦しみを取り除くために中絶は容認され
る。
6 )近親相姦の犠牲となった女性から,不必要な
苦しみを取り除き,遺伝的家族的混乱を避け
るために中絶は容認される。
7 )胎児が障害をもって生まれることが予想され
る場合,母親の心理的健康を損ない,家族に
緊張関係が生まれ,子供の低質な生活が予想
されるならば中絶は容認されるべきである。
8 )母親が子供の性別を選びたいと望む場合,あ
るいは胎児の身体組織が病気に悩む人々の苦
しみを取り除くために必要とされるような場
合,中絶は容認されるべきである。
ゲイリー・クラムはこの8点について,ひとつ
ひとつ丁寧に反論を試みているが,ここではその
内容には触れないこことしたい。
さて,プロチョイス派の陣営にあってひときわ
異彩を放っているのがRCRC,すなわち「産児選
択宗教連合」(The Religious Coalition for Repro-
ductive Choice)であろう。
このRCRCのモツトー
は,”Pro 于’aith, Pro 于’amily, Pro~Choice”であり,
「我々は信仰においてプロチョイス」,「祈りの姿勢
のプロチョイス」,「中絶は,道徳的,倫理的,宗
教的な責任ある決断であり得る」と謳っている。
(Gorman, 2003, 3 )
このRCRCは,プロチョイスとしての6つの
テーマを掲げている。
1)神が与えた性と出産にまつわる絶対的自由に
は,中絶の権利も含まれている。
2 )孤立する女性たちゃ十代の少年たちは,それ
ぞれが道徳的主権的存在である。
3 )出生前の人命の道徳的位置づけは,卑小化さ
れる。
4 )産児調整としての中絶の正当性
5 )中絶の神聖性
6 )聖書によって立証されるプロチョイスの神は,
24
生命主義とキリスト教
すべての選択を祝福する。
特に衝撃的なのは,「人工妊娠中絶」と「神聖さ」
が結びつけられている点であろう。
マイケル・
ゴーマン(Michael J. Gorman)とアン•ブルック
ス(Ann Loar Brooks)が,RCRCへの批判を記
した論文に”Holy Abortion?’,というタイトノレを
付けたのももっともなことである。
興味深いこと
にゴーマンとブルックスは,RCRCの中絶に対す
る態度は,キリスト教の歴史に見る戦争の取り扱
いとのアナロジーにおいてよく理解されると指摘
する。(Gorman, 2003, 30)
H 完壁主義¢ perfectionism)とプラグマ
ナズム(pragmatism)
2-1r正しい戰争」と「聖戰」
マイケル・ゴーマン(Michael J. Gorman)とア
ン・ブルックス(Ann Loar Brooks)は,中絶論
争を平和主義論争との類比において説明を試みて
いることは前述の通りである。
彼らは現代の主流
派キリスト教倫理における選択肢として,「絶対平
和主義」と「正しい戦争」を挙げている。
「正しい戦争」思想においては,致死的暴力は,
厳しい倫理的道徳的ガイドラインに照らして,た
だ最終手段としてのみ承認される。
戦争とは,あ
らゆる手段を講じて避けるべき,祝福されざるも
のとして認識される。
理論上,戦争は謙虚に改懐
の情をもって告発されるべきものである。
敵は人
間として取り扱われるべきであり,非戦闘員は標
的とはされない。
神の意志による戦争,あるいは
神に祝福された戦争というものは否定される。
悪
に満ちた世界では,戦争は状況に応じて人間の行
動として道徳的に正当化される。
しかしそれは決
して!_聖なるもの」ではありえない。(Gorm an,
2003, 31)
ここで注目すべきは,「正しい戦争」とは,いわ
ゆる「聖戦」とは区別されるということである。
「聖戦」とは,彼らが前述の文中で否定している
「神の意志による戦争,あるいは神に祝福された戦
争」のことである。
現代の主流派キリスト教会のなかで,正面切っ
て十字軍的「聖戦」を肯定する教派はない。
しか
しr聖戦」ではなく , r正しい戦争」を否定しない
教会は少なからず存在する。
そのひとつがルーテ
ル教会である。
ルーテル教会の信仰告白文書であ
魏アウグスブルグ信仰告白』の第16条において,
「正しい戦争」に従事することは正当であると謳わ
れている。
しかしここで再度確認されるべきは,
肯定されている「正しい戦争」においては,ゴー
マンとブルックスが定義するように,「敵は人間と
して取り扱われるべきであり,非戦闘員は標的と
はされない。」のであって,ときに胎児を「人格を
持たぬ存在」とし,無抵抗である胎児の命を奪
うことを是とする中絶容認の立場は,「正しい戦
争」のアナロジーとしてはふさわしくないと言わ
なければならない。
2-2プロチョイス陣営の混乱
もし「プロライフープロチョイス論争」を平和
主義論争の文脈で言い換えるならば,ライホンル
ド・ニーバー(Reinhold Niebuhr)が暴力容認の
是非について語る際に用いた用語を採用すべきで
あろう。
すなわち,「プロライフープロチョイス論
争」は,「完璧主義ープラグマチズム論争」である。
(Niebuhr, 1935,114)
もちろん,これでもまだ不
十分なアナロジーに止まることは承知の上である。
「プロライフ」の「絶対平和主義」「完璧主義」へ
の言い換えには,ほとんど異論がないものと思う。
一方「プロチョイス」を「正しい戦争」「プラグマ
チズム」とすることには,先の指摘にもあるよう
に各方面からの異論が予想される。
まず第一に,プロチョイス陣営は決して一枚岩
ではない。中絶ぜ女性の当然の権利」とする人々
にとっては,中絶は必ずしも「苦渋の選択」では
ない。ましてや「中絶の神聖性」を主張する人々
にとっては,中絶は「回避すべき選択肢」ですら
ないのである。しかしプロチョイス陣営に留まる
25
ルーテル学院研究紀要No.40 2006
人々の中には,「苦渋の選択」としての中絶の容認
を求める者も多く,その場合は「必要悪」として
中絶は容認されているに過ぎない。この立場であ
れば「正しい戦争」のアナロジーは一部有効とな
る。
さらにプロチョイス陣営の混乱を深くしている
のが,「胎児は人格を持った人間か否か?」につい
ての認識である。
プロライフ陣営はこの点につい
ては完全な一枚岩である。
彼らの主張によれば,
胎児はどの段階においても人格を持った完全な人
間であり,|_人間か否か?」という問いかけ自体が
ナンセンスなのだ。
しかしプロチョイス陣営のみならず,そもそも
生命倫理学的にも,胎児の人格発生時期について
の統一された見解というようなものはないので
あって,あるのはただ「胎児の生存可能性確立時
期」と「母胎の危機を避けるための基準」のみで
あり,「ロウ対ウェイド判決」が,「それ以降の中
絶禁止を法制化できる」としたのも後者の理由を
根拠としているのである。
キリスト教倫理学の最左翼ともいうべきジョー
ゼフ・フレッチャー(Joseph Fletcher)の見解は
以下の通りである。
最低限の理性と精神性を欠く存在は,たとえ身
体器官が機能しており,自発的生の過程にあると
しても,それは人間とはいえない。
もしも事故や
病気で大脳を失い,中脳と脳幹が自発的に機能し
ているとしても,それはモノであってヒトではな
い• • •脳のない生物体は人間ではないのである。
(Fletcher, 1979,135)
フレッチャーのように,理性や精神性をもって
人格の基準とする生命倫理学者は少なくない。
ただその理性・精神性の確立時期については,自己
認識の確立後であるとか,言語能力の獲得後であ
るとか様々な見解がある。しかしこれらの立場に
共通していることは,出生前に人格が確立すると
は考えられないという点にある。
またこれとは別に,胎児はまだ人間ではないけ
れども,しかし将来人間となる「可能性」をもつ
「いのち」であるから,やはり人格を持った人間と
同じように取り扱われるべきであるという主張が
ある。
しかしこのような「可能性論者」に対して,
フレッチャーは皮肉を込めて以下のように言い放
つのである。
反中絶論者はしばしばこのように言う。「とにか
く,胎児には人間となる可能性がある。たとえば,
形態上未発達だが精神の基礎となる身体組織は,
8カ月目には発生する。」と。
これは,事実として
胎児は人間ではないということを認めているのと
同じである。
この「可能性」イコールT現実性」で
あるという議論は,「どんぐりは樫の木である」,
「約束は履行である」あるいは「青写真は家であ
る」と主張するようなものである。(Fletcher,
1979,135)
この人格の確立時期についての議論に深入りし
ても,それがいわゆる「神学論争」に終始するで
あろうことは容易に予想がっく。
「神学論争」と
は,皮肉でそう言っているわけではない。
「いのち」の始まりと終わりについての議論は,どうし
ても「神学論争」にとならざるを得ないのであっ
て,そこでは自然科学の定義は用をなさないので
ある。
何をもって「人」とするかは,自然科学の
命題ではなく,むしろ人文科学の命題であり,神
学の命題である。
以上のような概観から導き出される「プロライ
フープロチョイス論争」のアナロジーには,やは
りニーバーの言う「完璧主義ープラグマチズム論
争」がふさわしいようである。
プラグマチズムは,
単純な真偽の二分法を否定する。
つまり,プロ
チョイス陣営に身を置きつつ,胎児の人格性を問
題とする人々にとって,どの時点での中絶は正で
あり,どの時点で誤となるのかを確定することは
困難であり,もしそれが多種多様な社会的•文化
的コンテクストを抜きにして論じられるのであれ
ば,実効性を伴った中絶の議論は成立しないとい
うことである。
26
生命主義とキリスト教
mキリスト教会としての対応
3 一1RCRC加盟教会の場合
前述の「産児選択宗教連合」(The Religious
Coalition for Reproductive Choice)には,現在4
つの主流派プロテスタント教会,すなわちユナイ
テッド・メソジスト教会,米国長老派教会,米国
聖公会,ユナイテッド・チャーチ・オブ・クライ
ストが加盟している。
しかし少なくとも,その4つの主流派教会のう
ちの3つについては,中絶は悲劇的な最終手段」
であって,通常は避けるべき事柄であり,容易に
許されることではないという考えを明らかにして
いる。(Gorm an, 2003, 33)
RCRCが掲げるプロチョイスの6つのテーマに
ついては既に触れたが,「中絶の神聖性」を含むす
ベての項目について,加盟団体が一致して賛意を
表しているわけではないということには留意すべ
きであろう。
前述の4つの主流派教会のうちで,
唯一RCRCの基本方針に最も近い態度を表明して
いるのがユナイテッド・チャーチ・オブ・クライ
スト(UCC)である。UCCは1987年の総会にて,
「中絶は『社会正義』の問題であり,(最終手段と
して)家族計画・産児調整の正当な手段であるこ
とを意味する」との決議を行っている。しかしそ
こでは同時に,「予期せぬ妊娠に直面している人
は,中絶する前に,出産して子供を育てるか,子
供を養子に出すかを考えるべきである」と勧めて
いる。(Gorm an, 2003, 42)
ゴーマンとブルックスの分類によれば,前述の
4つの主流派教会の中絶にまつわる公式見解は,
以下の4点に集約される。(Gorman, 2003, 34)
1)婚姻関係内における,契約的な責任あるセッ
クス
2 )キリスト者の共同体における意志決定
3) 出生前の人命の神聖さ
4) 産児調整のためでなく,苦渋の選択としての
み許される中絶
3-2米国福音ルーテル教会の場合
米国福音ルーテル教会(The Evangelical
Lutheran Church in America)は,かつて一度も
RCRCの加盟教会であったことはない。
1995年の
ELCA総会における「教会としてのRCRCへの協
カ」をめぐる決議は,778対101で否決されている。
(Gorman, 2003, 44) ELCAの教会としての公式
見解は,プロチョイスの立場表明は行わないとい
うことであり,中絶に関しては明確に「正しい戦
争」のアナロジーにおける「苦渋の選択」の立場
を表明している。
確かに全体教会としては,RCRCに賛同しない
ELCAであるが,もちろんそれはプロライフ陣営
への無条件の賛同をも意味するものではない。
そ
のことは,ELCA内の組織であるルーテル女性会
派(The Lutheran Women’s Caucus)が RCRC
の正式加盟団体となっていることを見ても明らか
である。1991年にELCAの総会において表明され
た「中絶についての社会的声明」は以下の通りで
ある。
子宮内で成長しつつある命は,生まれ出るため
の絶対的権利を持つわけではない。
同様に妊娠中
の女性は,妊娠を中断するための絶対的権利を持
っわけではない。
女性と,女性の子宮内で成長し
つつある命の両者への関心は,共通の生命への責
任として表明される••・
我々は神が命の創造主であ
ると信じる。
ゆえに数多く行われている中絶行為
は,本教会にとっての深い憂慮の源となっている。
我々は神が造られた命が失われることを悼む。
キリスト者として強く望まれることは,命を守り保
っことである。
中絶は,ただ選択の最終手段とし
てのみあるべきである。(し
ELCAの社会的声明には,中絶をめぐる議論に
おいては,一般論としての「プロライフープロ
チョイス」という立場を超えた視点が求められる
ということが記されている。
ELCAは,既に述べ
たとおり「全米プロライフ宗教協議会= NPRC」へ
の賛同者も,「産児選択宗教連合=RCRCJへの賛
27
ルーテル学院研究紀要No.40 2006
同者も内包する教会組織である。このような対立
の一致については,妥協や諦念とは違ういわば
「信仰における一致」を目指す寛容さが求められる
のであろう。
~結語〜
プロライフ陣営に属する牧師•司祭の主張には,
それなりに首肯できる部分もある。
中絶を回避す
るために,女性を教会においてあらゆる方法で支
援するという主張は頼もしい。
しかし,現実に望
まない妊娠を続ける女性を,出産まで,あるいは
出産後も,時間的・空間的・財政的・精神的に支
援し続けることは容易なことではない。
プロチョ
イス陣営のある研究者の言葉を借りて言えば,「中
絶をやめて養子縁組させるべきだ」というお手軽
な勧めは,中絶をめぐる議論においては,誰にで
も思いつく「バンパー・ステッカー・レベル」の
発想でしかないということになる。点)
中絶を法律で禁じたところで,何も良い結果が
生まれないことは,「ロウ対ウェイド判決」以前の
米国の状況を見れば明らかである。
性教育の徹底
はもちろんのことであるが,つまるところ我々の
社会が,どこに向かって何を目指そうとするのか
という社会的なコンセンサスが得られない状況で
は,技術論的な性教育は無力である。
また一方で,「中絶は神に祝された行為である」
ということににわかに賛同することもできない。
「正しい戦争」を「聖戦」に昇格させることは,「物
言わぬ生命の軽視」という恐ろしい弊害をもたら
すに違いない。
さて,最後に我が国日本に目を転じてみたい。
この国は揶揄されているように「中絶天国」なの
であろうか?
米国ペンシルバニア大学で日本思想
を講じるウィリアム・ラフルーア(William R.
LaFleur)は,その著書において日本固有のT水子
供養」の普及に着目し,日本人が中絶をどのよう
に合理化してきたかについて解明を試みている。
ラフルーアによれば,初期仏教の戒律においては,
殺生の禁止は胎児の中絶にも及ぶものであったは
ずだが,中絶は胎児を神仏の世界に一時的に「カ
エス」ことによってやがて「黄泉がえる」という
考え方が普及したために,間引きを殺人と同一視
することはなくなったという説を紹介している。
ただ,このことによって日本人は中絶について全
<良心の呵責を感じなくなったのかといえば,そ
うではないとラフルーアは言う。
事実,中絶経験
者の多くが水子供養を望み,水子儀式を引き受け
る寺院に奉納される絵馬の多くには,水子への謝
罪の言葉が書き連ねられており,そこには日本人
の深い罪意識が反映されているとラフルーアは指
摘する。
このことは,『菊と刀』を記したルース・
ベネディクト(Ruth Benedict)の「恥の文化」説
を否定する証拠であるとまで言うのである。
ラフ
ルーアの目下の関心は,水子供養が日本のキリス
卜教にどのように取り入れられるのかという点に
あるという。(LaFleur,1992)
「人命は地球より重い」という言葉は,いつどこ
ででも通用するわけではない。
ジョーゼフ・フ
レッチャT Joseph Fletcher)の言葉を借りれば,
もしいついかなる時も「人命が地球より重い」の
であれば,英雄的行為や殉教,正当防衛における
殺傷などの行為には,倫理的根拠を提供すること
はできないということになる。(Fletcher,1988)
人工妊娠中絶は,よく言われるように「神を演じ
ること」なのだろうか?それとも,神の委託によ
る責務なのだろうか?
私はこの点については後者
を支持する。
しかしこのことによって,生命の神
聖性が帳消しになるということは許されるべきで
はない。
人工妊娠中絶はあくまで苦渋の選択」と
してのみ成立するのであって,そこには 慰め」は
あるが「祝福」はない。
キリスト者の立場で言え
ば,「神の委託による責務」こそ,地球より重いと
知るべきであろう。
我々は,神に無断でそうして
いるのではなく,神の委託を受けた管理者
(steward)として判断し行動するのである。
人間は,いつ人格を獲得するのか?人間を人間
としているものは一体何なのか?いわゆる生命主
義の優れた点は,その立場上「弱者」と目される
存在の権利を保障できるという点にある。
しかし,
28
生命主義とキリスト教
その生命主義があたかも機械論的・決定論的に例
外なく主張されるのであれば,私たちが「神の委
託に忠実であろう」とする自由意志そのものが無
意味であるということにもなりかねない。
20世紀
のいわゆる生気論論争は,あらゆる生命現象は物
理的・化学的法則によって説明可能であるという
機械論側の圧倒的勝利に終わった。
しかしその結
果が,昨今の風潮である「いのちの軽視」という
形で現れていることを,誰が否定できるだろう
か?
聖書原理主義の発想から,進化論を否定する
ような知的創造論を持ち出したいとは思わない。
しかし,生命の神聖性(Sanctity of Life)は,生
命の質(Quality of Life)と同様に重視されるべき
ものである。
もし世の中の様々な価値観が中絶を選ばせるな
らば,そのような価値観を覆すために心血を注ぐ
べきである。可能な限りの支援にもかかわらず,
それでも中絶を選ばざるを得なかった者には,心
からの慰めを祈るべきである。
現実的には,現在の我々に決定的に欠けている
ものは,人命尊重の倫理・道徳的規範などではな
い。
欠けているのは,中絶を選ぼうとする人たち
に実現可能な他の選択肢を用意するための努力で
ある。苦渋の選択をなそうとする女性と,生まれ
出ようとする胎児。その両者の隣人となることこ
そ,我々の最終目標である。
参考文献
Baird, Robert, M. and Rosenbaum, Stuart, E. eds.( 2001)
The Ethics of Abortion, New York: Prometheus
Books.
Crum, Gary, and McCormack, Thelma,(1992) Abortion:
Pro-Choice or Prolife?, The American Univer-
sity Press.
Fletcher, Joseph¢ 1979) Humanhood: Essays in Biomedi-
cal Ethics. New York: Prometheus Books.
Fletcher, Joseph¢ 1988) The Ethics of Genetic Control.
New York: Prometheus Books.
Gorman, Michael, J. and Brooks, Ann, Loar,( 2003) Holy
Abortion?: A Theological Critique of the RCRC.
Eugene, Oregon: Wipf and Stock Publishers.
教皇庁教理省(1987l生命のはじまりに関する教書』カ
トリック中央協議会
LaFleur, William, R.(1992) Liquid Life: Abortion and
Buddhism in Japan. Princeton University Press.
(二2006,ウィリアム・R・ラフルーア著 森下直貴
ほか訳『水子』青木書店)
Niebuhr, Reinhold/ 1935) An Interpretation of Chris-
tian Ethics. San Francisco: Harper & Row .
Pence, Gregory, E.( 2000) Classic Cases in Medical Eth-
ics, New York: McGraw Hill Companies, Inc.( =
2000,宮坂道夫・長岡成夫訳T医療倫理1』みすず
書房)
Stallsworth, Paul,T. ed.(1997) The Right Choice,
Nashville: Abingdon Press.
註
(1) Second biennial Churchwide Assembly of the
Evangelical Lutheran Church in America, 1991,
A Social Statement on Abortion;
www .elca.org/socialstatem ents/abortion
(2 ) Maguire, Daniel,C. A Catholic Theologian at an
Abortion Clinic, Baird, Robert, M. and Rosenbaum,
Stuart, E. eds( 2001)The Ethics of Abortion, New
York: Prom etheus Books. 201
29
ルーテル学院研究紀要No.40 2006
Vitalism and Christianity:
一 Learning from the Pro-Life and Pro-Choice Arguments in the United States 一
Tajima, Yasunori
In Japan, it is believed that there is a vitalistic view of value, expressed in the phrase “human life is heavier
than the earth.^^ On the other hand, we have a generous tolerance toward abortion. Therefore this country has
been labeled dishonorably as “an abortion paradise.” In the United States, the abortion issue, framed between
the pro-life and pro-choice arguments has been a significant conflict that has divided the country into two
parts. Christianity, which exerts an important influence on the judgment of ethical values in the U.S., continues
to debate with interesting responses. In this article, we will listen to Christian people who belong the National
Pro-life Religious Council and the Religious Coalition for Reproductive Choice. These different opinions,
which are held within the same Christian faith, contemplate what it means to be a neighbor for both women and
fetuses.
Key Words : Abortion, Vitalism, Pro-life vs. pro-choice, National Pro-life Religious Council, Religious Coa-
lition for Reproductive Choice
30