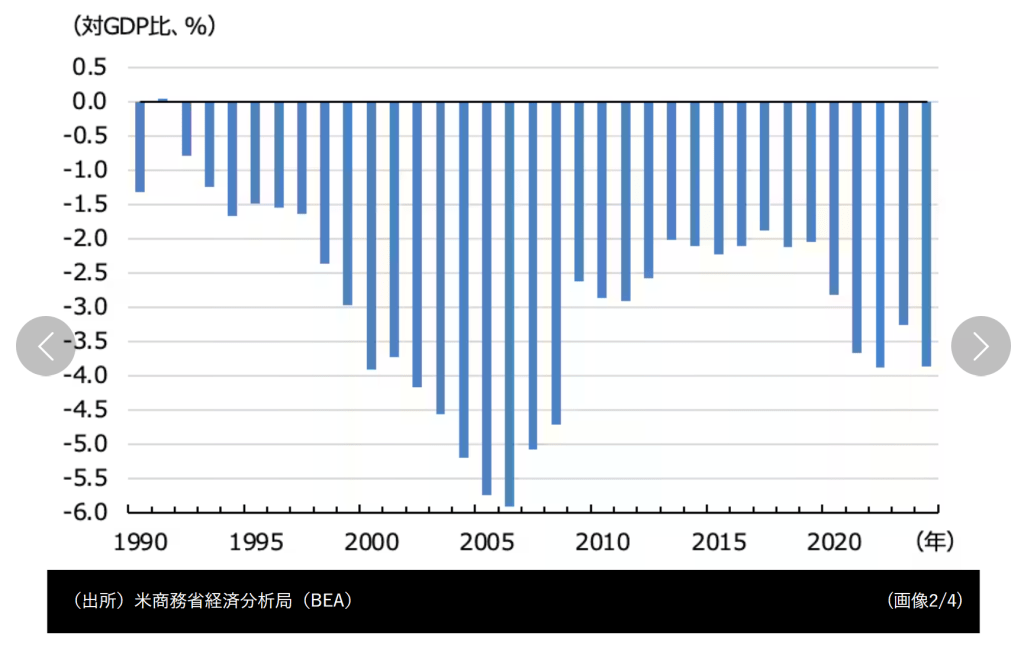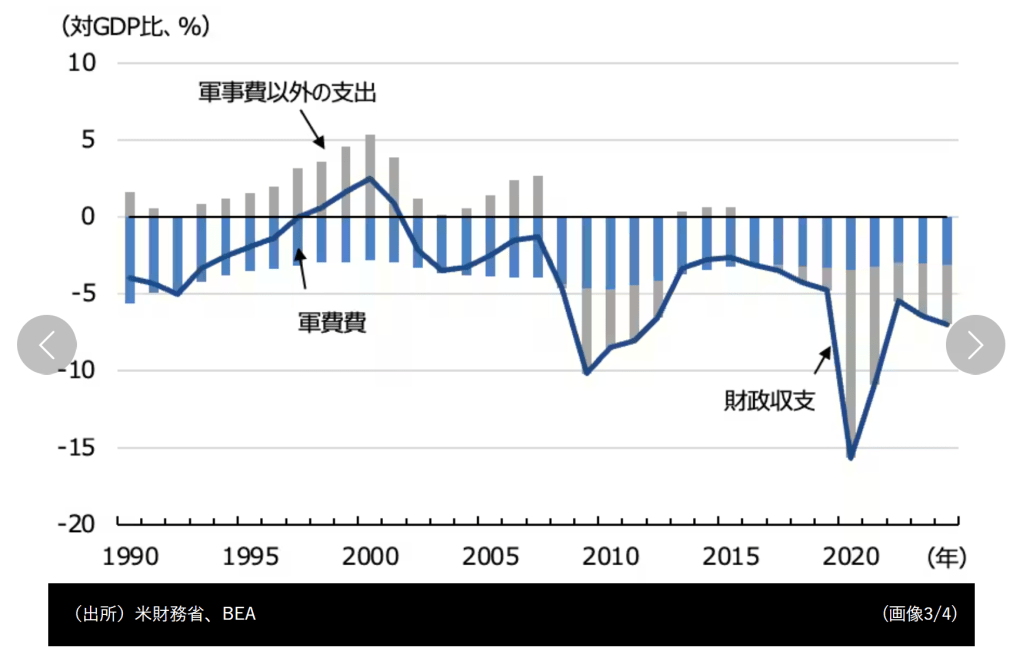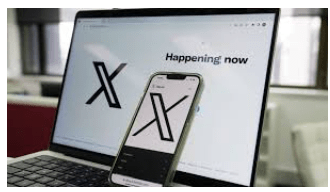https://www.jstage.jst.go.jp/article/kokusaianzenhosho/50/1/50_115/_pdf/-char/ja
国際安全保障第50巻第1号
115
【書評】
岩間陽子著
『核の一九六八年体制と西ドイツ』
(有斐閣、2021年8月)400頁
田中慎吾
序章によれば本書は、冷戦下において常に存亡の危機にあった西ドイツが、
いかなる目的・経緯によって1968年の核不拡散条約(NPT)を基底とする、核
に関する世界的な不拡散秩序(「核の1968年体制」)に参加したのかを問うもの
である。
第1章「核戦略の誕生」では、原子爆弾や戦略爆撃の誕生過程を概観した後、
アメリカのアイゼンハワー (Dwight Eisenhower)政権が核兵器を使用しうる兵
器として「大量報復戦略」を採用した経緯が記される。
第2章「大量報復戦略と西ドイツ」では、アイゼンハワー政権は次の二つの
方法で欧州に大量の戦術核を搬入したことが記される。
第1に在欧米軍への配
備であり、第2に後に「核共有」という呼び名で総称されることとなる、核弾
頭を平時は米軍が管理し、同盟国は運搬手段を保有する方法であった。
西ドイ
ツには1955年5月の主権回復とNATO加盟以前より、前者の方法で多種多様な
戦術核が大量に搬入されたことが紹介されている。
同年11月、NATOが正式に
大量報復戦略を採用し、核兵器の使用を前提とした防衛計画に移行したことに
対し、当時の西ドイツ首相アデナウアー(KonradAdenauer)は否定的であっ
たという。
彼は核兵器への道徳的嫌悪から核軍縮を優先し、その後に通常兵器
を削減するべきだと主張していたのであるが、ハンガリー動乱とスエズ危機を
経てNATOの方針を受容するに至ったことが記されている。
第3章「米英「核同盟」と危機の季節」では、アイゼンハワー政権が1957年
10月4日のスブート二ク・ショック以前より、アメリカの核兵器をNATOの管
理下に置く「核備蓄」制度の検討を始めており、同年12月のNATOサミットに
て同制度が正式に提案されたことが先ずは指摘される。
しかし1958年に米英間
で相互防衛協定が締結され、核分野における「特別な二国間関係」が構築され
116
2022年6月
た結果、NATO内に亀裂が入ったことが記されている。
また、同年11月の第2
次ベルリン危機からキューバ危機を経て、アイゼンハワー政権末期に策定され
た初めての核戦争計画「単一統合作戦計画(SIOP)62」の非人道性と非現実性
が明らかとなり、続くケネディ(JohnKennedy)政権下において「柔軟反応戦略」
への移行が加速されたことが示されている。
第4章「「N番目」の核保有国」は、評者が最も面白いと感じた章であった。
スプートニク•ショックによって生じたアメリカの抑止力に対する欧州同盟国
の懸念を打ち消すべく、アメリカが欧州へ核兵器を搬入し始めたことは良く知
られているが、筆者によればイギリスへの搬入は、米英双方がまさに物理的な
鍵を所有する「二重鍵(double-key)」システムを採用する例外的な事例であっ
たという。
また、イギリスへの配備が二国間の枠組みであったのに対し、トル
コとイタリアへの配備はNATOの枠組みによるものであり、欧州連合軍最高司
令官が受入国とアメリカ政府と合意の上で使用の判断を下すことになっていた
と筆者は指摘する。
さらには西ドイツも自国への中距離核ミサイルの配備を望
んでいたが前線に近過ぎるとして見送られ、フランスは自国のみで使用を決定
できないことに不満を持ち配備を辞退したことも紹介されている。
ただ、こうしたヨーロッパに配備された中距離核は脆弱性の高さから暫定的
措置であり、アイゼンハワー政権内にはNATOとしての核抑止力を創設するべ
く、「NATO核戦力(NNF)Jや多国籍乗組員から構成されるポラリス潜水艦に
よる「NATOの抑止カ(NADET) J計画などが存在していたとの指摘は興味深
いものであった。
同章後半においては、ケネディ政権があくまでも欧州通常兵力の増強を優先
し、NATOの「多角的核戦力」(MLF)構想には消極的であり、MLFの構成を
潜水艦から水上艦へと変更していたことが指摘される。こうしたケネディ政権
の姿勢に対して西ドイツが反発し、最終的に1963年1月22日の独仏友好条約(エ
リゼー条約)の調印に至ったことが描かれている。
第5章「核の一九六八年体制への道」では、NATOが1963年10月から正式に
MLFの検討を始めた一方で、ケネディ暗殺に伴い急遽登板したアメリカのジョ
ンソン(Lyndon Johnson)政権は前政権同様にMLFに否定的となり、ソ連との
NPT締結に関心を移していったと筆者は指摘する。
ジョンソン政権は1964年10
月の中国による核実験を契機としてNPT交渉を本格化させ、その過程において
核兵器そのものの共有を目指すMLFではなく、核戦略の協議制度の構築を目
指したことが指摘されている。これを受けてNATOは1966年から67年にかけて、
国際安全保障第50巻第1号
117
フランスがMLFを拒否してNATO軍事機構から離脱したこともあり、MLFを棚
上げして核共有計画グループ(NPG)なる協議制度を創設したことが記されて
いる。
第6章では章題「西ドイツと一九六八年体制の受容」が示すとおり、西ドイ
ツ内の政治過程が描かれる。
筆者によれば1966年12月誕生のキージンガー(Kurt
Kiesinger)大連立政権はNPT交渉の詳細を知らされておらず、米独関係は悪化
していたという。
アメリカはNPTの対ソ交渉において、NATOの二国間核共有
制度が影響を受けないこと、統一ヨーロッパが将来に核保有国となる権利を排
除しないこと、核運搬主段やシステムの保有またはコントロールの移譲は規制
の対象としないことを主張した結果、ソ連はアメリカがそのような発言をする
権利に異議を唱えないことで妥協したことが示される。
こうして成立に至った
NPTは、西ドイツ内では反対論が根強く署名の見込みが立たなかったものの、
ブラント(Willy Brandt)外相は、西ドイツとソ連間の関係改善を皮切りにヨー
ロッパの緊張緩和を目指すという自らの東方政策、自らのヨーロッパ外交を展
開する前提条件として、NPT署名の必要性を明確に認識していたと筆者は指摘
する。
実際、ブラントが1969年10月に政権を獲得すると、1969年11月28日に署
名を行ったのであった。
以上を踏まえて終章では、「核の1968年体制」とは何かを改めて概説した後、
NATOの核共有はあくまでも政治的シンボルであったとし、NPGのような協議
制度も戦術核使用において何ら合意に達していなかったと指摘する。
最後に筆
者は、こうした核の秩序体制が今後も生き延びられるかの大きな曲がり角に現
在さしかかっていると警鐘を鳴らす。
特にロシアが核大国であることの責任を
果たし続けるのか、それとも矮小な国益のために、これまで半世紀にわたって
維持してきた体制にダメージを与えるような行動に走るのかとの筆者の懸念
は、まさに正鵠を射ていたものといえよう。
さて、これまでにもNPT体制の成立過程を論じた学術書は国内外に多く存在
してきたものの、それら大半はアメリカの核兵器不拡散外交の変遷を論じるも
のや、軍縮委員会の議論に焦点を置いたものが大半であった。
それら類書と
大きく異なり本書は、西ドイツが自国の外交•防衛政策として、いかにNPT体
制を位置付け、いかなる目的をもって受容したのかの解明を主目的としつつ
も、ベルリン危機といった冷戦の推移にも目を配り、それらがいかに絡み合っ
て核共有制度や核不拡散制度の形成に至ったのかをも論じる大変意欲的な構成
となっている。
こうした本書は、ドイツの外交•安全保障政策を長年研究して
118
2022年6月
きた筆者にしか書くことが出来ないものであり、学術的に極めて大きな意義を
もっている。
以上を踏まえた上で本書の問題点を挙げるのならば、それは読み難さである。
この読み難さの要因は主に、章や節で時代が前後し、また、説明も前後ないし
重複している箇所が多いことに求められる。
さらに本書の読み難さには、以下二つの要因も関係しているように思われる。
第1に、特定の経緯の説明を省略していることである。
例えば189頁において筆
者は、MLFの構成を潜水艦から水上艦へと変更したことについて、複数の理
由からアメリカが修正したとするのみで、その説明を省いている。
また、238
頁においては、イギリスのウィルソン(Harold Wilson)政権がアメリカのMLF
案を修正して大西洋核戦略(ANF)構想を提案したと紹介されているが、脚注
においても文献紹介にとどまっており、ANF構想に具体的説明がないままに以
降はMLF/ANFと併記されていく。
評者はこれらの点を疑問に感じたまま本書
を読み進めなければならず、これが読み難さにつながっているように思われた。
第2に、核関連用語に対する説明の不十分さである。
本書には核兵器、原子
爆弾、水爆、熱核兵器や熱核物質といった各種の用語が登場するが、本書はこ
れらを十分に説明せぬまま、そして相互に関連づけぬまま使用しているのであ
る。
おそらく筆者は、核兵器とは一般的に原子爆弾と水素爆弾に大別され、前者
はウランやプルトニウムなどの重い原子核を分裂させた際に生ずるエネルギー
を利用したものであること、後者が重水素や三重水素による軽い原子核を融合
させた際に生ずるエネルギーを利用したものであること、さらには、後者が核
融合は分裂よりも高熱を発することから熱核爆弾との別名が存在することにつ
いては、核問題の専門家にとっては常識の範疇と判断し、説明を省いたのであ
ろう。
しかし本書は、冷戦史やヨーロッパ政治史など多くの専門家に読まれる
であろうから、これら用語についても丁寧な説明が必要であったと評者は考え
る。
とりわけ評者は、「放射能」の使用方法が気にかかった。
例えば58頁におい
て筆者は、「放射能に対する防御」や「放射能からの保護」と記述する。
こう
した用法でも日本語的に意味は通じるように思われるが、本来「放射能」とは、
原子核が崩壊する際に放射されるヘリウム(α粒子)や電子(0粒子)などの粒
子や電磁波といった各種の放射線を出す能力を指し示す用語のはずである。っ
まり厳密には放射能ではなく「放射線に対する防御」や、「放射線からの保護」
国際安全保障第50巻第1号
119
と表記すべきではなかったのだろうか、。
もちろん日本では、「放射能」が何か恐ろしいものという意味合いで広く用
いられていることは事実である。
それゆえ、もし本書がドイツ外交史として核
不拡散体制の受容過程を描くだけの内容であったのならば、問題にすべきで点
は無かったのかもしれない。
しかし本書は、国際政治における核兵器を真正面
から取り上げ、その秩序の形成と受容を捉える意欲的なものである。
そうであ
るならば本書の信憑性に要らぬ疑義を生じさせないためにも、核関連の用語に
ついては曖昧な用法を避けるべきであったと評者は考える。
また、確認できる限り序章から第4章までは、各章に最低一つは誤字脱字が
存在していることも極めて残念な点であると言わざるを得ず、これも読み難さ
につながっているように思われた。
以上、長年に渡る筆者の研究成果を多く詰め込んだ本書から得られる知識の
量は膨大であり、それら一つ一つは極めて重要なものである。
ただ、読みやす
さの観点からすると評者は、国や時代、あるいは核共有やNPT体制といった卜
ピックにおいて、もう少し視野を絞るなどの工夫があっても良かったように思
う。
その点、あくまでも評者の個人的所見としては、第2次世界大戦下のドイ
ツ内での核研究が戦後のドイツの(非)核政策にいかなる影響を及ぼしたのか
についての言及が本書前半にあると、本書が(西)ドイツの視点から一貫して
記述しているとの印象を読者に与え好ましかったように感じた。
(たなかしんご 大阪経済法科大学特別専任准教授)